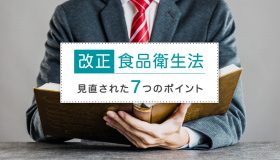HACCP導入のための「7原則12手順」とは?

実施するための原則と手順
HACCPは、組織全体で適切に実施することが求められます。そのため、HACCP導入の決定後は、HACCPチームを編成して、定められた原則と手順に沿って、運営方法を決定していくことになります。それが下記の「7原則12手順」です。
- (手順1)HACCPを実施するチームを編成する
- (手順2)レシピや仕様書といった製品の説明書を作成する
- (手順3)意図される使用方法を確認する(加熱の有無など)
- (手順4)製造工程(受け入れ~提供まで)の一覧図を作成する
- (手順5)手順4の製造工程図をもとに、現場での人・モノの動きを確認・修正する
- (手順6)【原則1】危害要因を分析する
- (手順7)【原則2】必須管理点を設定する
- (手順8)【原則3】管理基準を設定する
- (手順9)【原則4】モニタリング方法を設定する
- (手順10)【原則5】管理基準から逸脱があった場合の是正措置を設定する
- (手順11)【原則6】検証方法の手段を設定する
- (手順12)【原則7】記録・文書化・保管システムを確立する
※手順1~5は、原則1~7を進めるための準備となります。
導入レベルは「A」と「B」の2段階
「7原則12手順」は、HACCPに基づく衛生管理を、効果的かつ効率的に実施するために示されています。しかし業種・業態によっては、これらの順守が困難な場合もあります。そこで厚生労働省では、HACCPの制度化に伴い、2つの基準を設定する予定です。
「基準A」…HACCPの7原則に基づく衛生管理
「基準B」…HACCPの7原則の弾力的な運用を可能とするHACCPの考え方に基づく衛生管理
「基準B」は、どう弾力的なのか?
ここで気になるのは、「基準B」が、どこまで弾力的な運用になるのかという部分です。基準Bでは、要求事項である「危害要因分析」「モニタリング頻度」「記録作成・保管」で緩和措置が示される方針で進んでいます。
具体的な例を挙げるならば…
・加熱による食材変化は目視確認でOK
・業態ごとに作成される手引きに沿って日誌作成を行い、それを記録保管とみなす
など、柔軟性を持たせた対応策が検討されています。
組織対応が求められるHACCP

「基準B」が設けられる方針とはいえ、食品に求められる安全基準は、「基準A」も「基準B」も大きく変わることはありません。そのため、これらの原則・手順に沿ってHACCPを導入するには、組織としての取り組みが必要になります。
フクシマガリレイでは、HACCPでいえば原則4、原則7に該当する「記録付け→文書化→保管」の部分を自動化させる、情報通信技術もご提案しています。企業内で確保できる人員に限りがあるからこそ、最も重要となる人的コストを、効率的に動かすためのサポートもお任せください。