HACCP導入「7原則12手順」 「(手順2)製品説明書の作成」 「(手順3)使用用途、対象者の確認(加熱の有無など)」
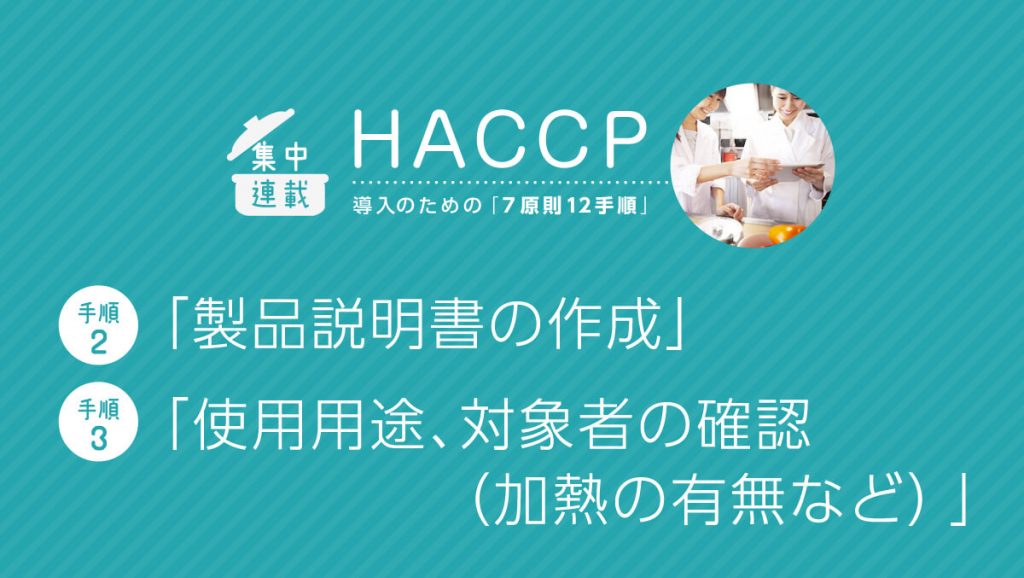
衛生管理手法であるHACCPは、組織全体で適切に実施することが求められます。その際に役立つのが、HACCPの運営手順をまとめた「7原則12手順」です。
近い将来、HACCPが義務化されても焦らなくていいように、各原則・手順についてきちんと内容を把握しておくことが必要となります。そこで、7原則12手順の詳細をそれぞれ解説しました。本記事では、「(手順2)製品説明書の作成」と「(手順3)使用用途、対象者の確認(加熱の有無など)」について詳しくまとめています。
危害分析のためにも必要な「製品説明書」を作成する
手順2と手順3は「製品説明書」を作る工程です。
すべきことは、大きく分けて2つあります。1つは、衛生管理を行うにあたって、製品の情報(仕様や特性)を明確にしておくことです。そのため、最終製品について、さまざまな項目に分けて仕様や特性を記述する必要があります。
そして、2つ目は、製品が「誰に、どのように」喫食・使用されるのかを明確にすることです。これは、製品の管理レベルに影響を及ぼすもので、内容によっては特に安全性に気を配らなくてはならないケースなども見えてきます。
こうした情報をまとめて、わかりやすく表にしたものが製品説明書です。表にすることにより、漏れが無くなり、危害分析等にも役に立ちます。
「製品説明書」に記載が必要な項目とは
製品説明書に決まった書式はありませんが、主に下記のような項目に添って情報を集め、まとめていきましょう。
-
「製品の名称及び種類」
商品名や販売している名称等をそのまま記載します。
種類を記載するのは、食品の種類によって成分規格、製造基準が異なるためです。 -
「原材料の名称や種類」
製品を製造、加工、調理する際に使用する原材料すべてに関する情報を記載します。
記録すべき情報は、名称、入手先、産地、製造者、製造方法などです。
アレルギー表示の必要な材料は、特に忘れず記載することが必要となります。また、使用する水についても、水道水なのか井戸水などかの記載が求められます。 -
「添加物の名称および使用量」
製品中に含まれる添加物の名称と使用量を記載します。
使用量を記載するのは、使用基準のある添加物について注意して取り扱うためです。 -
「容器包装の材質および形態」
実際に使用する包材の材質および形態について、名称などを記載します。
-
「製品の特性や規格」
製品特性(安全性、保存性に影響するような特徴)について記載します。
pH・糖度・水分活性等の情報をも必要に応じて加えてください。 -
「保存方法」
製品の保存方法について記載します。
-
「消費期限または賞味期限」
安全性に配慮するために大事な項目である、消費期限または賞味期限について記載します。
-
「喫食や販売の対象者」
完成した製品を口に入れるのは、主に誰なのかについて記載します。
対象は、一般消費者・入院患者・乳幼児など、特性や年代をわかる範囲で詳しく書いてください。この対象が誰なのかによって、より厳しい安全性の確保が必要になるケースがあります。 -
「喫食または利用の方法」
製造した製品が、どのようにして口に入るのか(そのまま喫食されるのか、加熱するのか)や、他の食品の原材料に使われるのかどうかを記載します。
正確な情報の詰まった製品説明書の作成が大切
製品説明書を作成する際には、取引先から入手できる原材料や容器包装の仕様書を活用することもおすすめです。
この後の工程で行う危害分析をスムーズに進めるためにも、各部門から集まったHACCPチームメンバーで、必要な情報をしっかり集めて、製品説明書を充実させましょう。
7原則12手順の一覧
- HACCPチームの編成
- 製品説明書の作成
- 用途、対象者の確認(加熱の有無など)
- 製造工程一覧図の作成
- 製造工程図をもとにした現場確認
- 【原則1】危害要因の分析
- 【原則2】必須管理点の設定
- 【原則3】管理基準の設定
- 【原則4】モニタリング方法の設定
- 【原則5】管理基準逸脱時の是正措置の設定
- 【原則6】検証方法の設定
- 【原則7】記録・保管システムの確立
※手順1~5は、原則1~7を進めるための準備となります。




