HACCP導入「7原則12手順」 (手順6)【原則1】危害要因の分析
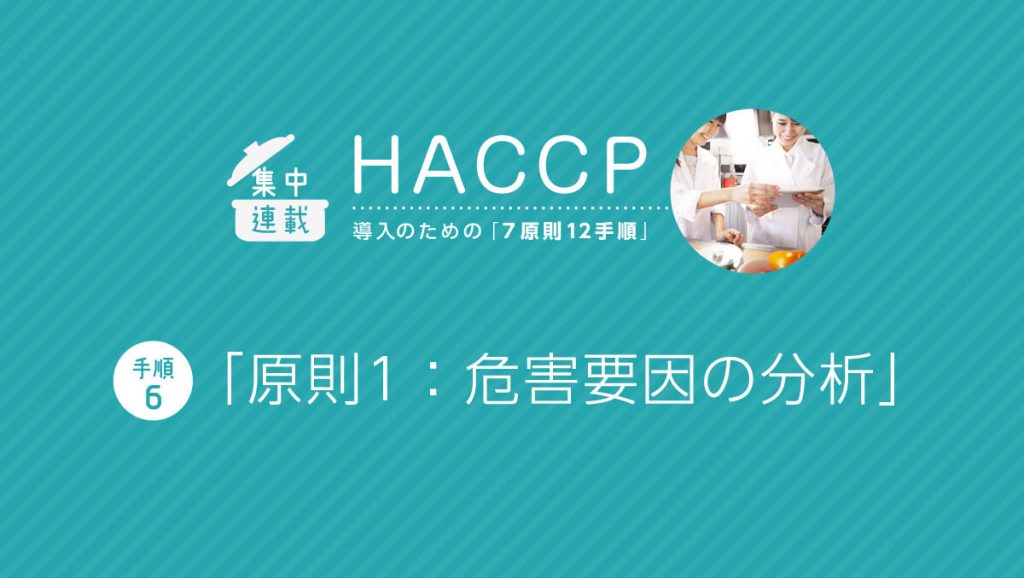
衛生管理手法であるHACCPは、組織全体で適切に実施することが求められます。その際に役立つのが、HACCPの運営手順をまとめた「7原則12手順」です。
近い将来、HACCPが義務化されても焦らなくていいように、各原則・手順についてきちんと内容を把握しておくことが必要となります。そこで、7原則12手順の詳細をそれぞれ解説しました。本記事では、「(手順6)【原則1】危害要因の分析」について詳しくまとめています。
工程ごとに潜んでいる危害要因とその対策を考える
危害要因の分析においては、工程ごとにどのような危害要因が潜んでいるのかと、その被害の重大性を考えていくことが必要となります。もちろん、挙げられたそれぞれの危害要因に対しての対策や管理手段(方法)も考えなければなりません。
そのためには、まず原材料から製造加工・保管・流通を経て消費に至るまでのすべての過程において、発生する可能性のある危害要因とその発生条件などについての情報を収集することが求められます。情報が集まったら、それらを一覧できる危害要因分析表を作成しましょう。
危害要因分析表に必要な情報の要素とは
危害要因分析表は、下記のような項目をベースに情報をまとめてください。
〈項目例〉
-
原材料/工程
対象となる原材料や工程を記載します。
-
1欄で予想される危害要因とは
予想される危害要因について記載します。「危害要因」とは、食品中に含まれる、健康に悪影響をもたらす可能性のある物質や食品のことで、主に下記の3種類に分類されます。
①生物的:原料由来あるいは工程中に汚染を受ける可能性がある微生物
②物理的:金属、ガラス、硬質プラスチックなど、混入する可能性がある硬質異物
③科学的:原料に残存している可能性がある農薬、誤って混入する可能性がある化学物質 -
重大な危害要因か(Yes/No)
予防、除去が必要で重大なものはYes、そうでないものはNo記載します。基本的に、一般的衛生管理マニュアルで対応できるものはNoにして大丈夫です。
-
3欄の判断を下した根拠
どういった理由から重大or重大じゃないとみなしたのか、その根拠を記載します。単なるYes/Noだけでなく根拠も明記することで、重大な危害要因の見逃しなども防ぐことができるためです。
-
3欄でYesとした危害要因の管理手段は?
どういった管理手段もしくは対処を施すことで、危害要因を予防・除去するのか、その具体策について記載します。
-
CCPか(Yes/No)
「CCP」とは、「必須管理点」のことで、以降の工程で危害要因を除去・低減する工程が無いことを指します。つまり、CCPがYesということは、ここで必ずしっかりとした危害要因の予防・除去を行わなければいけないという確認の意味にもなります。
こうした項目に添って情報をまとめて危害要因の分析を行い、決定したCCP(必須管理点)を継続的に監視することが、製品の安全確保につながるのです。
※「CCP」についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
危害要因分析はHACCPの心臓部分、安全管理の要
危害要因分析を行う際に大切なのは、見落とす危害要因が無いよう、その製品に関わるすべての部署の担当者で行うことです。そうすることで、皆に情報が行き渡り、同じ危険要因を共有できて全体の衛生意識が向上するという利点もあります。
起こりうる危害を先回りして分析し、その対策を立てるこの工程は、HACCPの心臓部分とも言われるほど、現場の安全管理においてとても重要になります。ここでしっかりと危害要因を洗い出すことによって、危害を未然に防ぎ、万が一危害が生まれた際にも最小限に抑えることが可能です。そのため、協力して情報を集め、丁寧に分析を行いましょう。
7原則12手順の一覧
- HACCPチームの編成
- 製品説明書の作成
- 用途、対象者の確認(加熱の有無など)
- 製造工程一覧図の作成
- 製造工程図をもとにした現場確認
- 【原則1】危害要因の分析
- 【原則2】必須管理点の設定
- 【原則3】管理基準の設定
- 【原則4】モニタリング方法の設定
- 【原則5】管理基準逸脱時の是正措置の設定
- 【原則6】検証方法の設定
- 【原則7】記録・保管システムの確立
※手順1~5は、原則1~7を進めるための準備となります。




