HACCP導入「7原則12手順」 (手順7)【原則2】必須管理点の設定
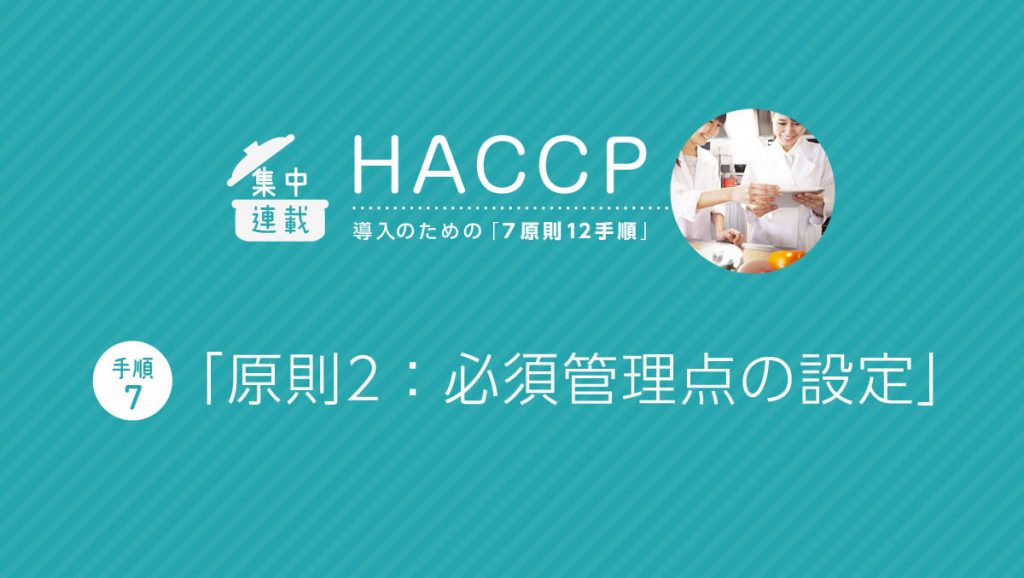
衛生管理手法であるHACCPは、組織全体で適切に実施することが求められます。その際に役立つのが、HACCPの運営手順をまとめた「7原則12手順」です。
近い将来、HACCPが義務化されても焦らなくていいように、各原則・手順についてきちんと内容を把握しておくことが必要となります。そこで、7原則12手順の詳細をそれぞれ解説しました。本記事では、「(手順7)【原則2】必須管理点の設定」について詳しくまとめています。
必須管理点(CCP)が明らかになることで効率的に食品の安全を確保できる
手順6でも少し触れましたが、この工程では「必須管理点(Critical Control Point)」を決める必要があります。
必須管理点(CCP)とは食品衛生を管理する上で特に気にかけるべきポイントのことです。たとえば、危害要因としてあげられた微生物が、最終殺菌・低減される工程が必須管理点(CCP)にあたります。これはつまり、「この作業以降で殺菌・低減するタイミングはないから、ここでしっかり取り除く必要がある」ということを意味しているのです。
こうした必須管理点(CCP)を明らかにしておくことで、より注意してその工程のモニタリングを行うことができ、効率的に食品の安全を確保することができるのです。
必須管理点(CCP)の決め方
必須管理点(CCP)は、特に気にかけるべきポイントなので、多くありすぎてもその意味をなしません。一般的には、5箇所以内に抑えることが望ましいとされています。
「ここが必須管理点(CCP)である/必須管理点(CCP)でない」の判断軸としては、公共社団法人日本食品衛生協会の「HACCPシステムとその適用のためのガイドライン」内に記載されている、「CCPを確認するための決定樹の例」を参考にしてみてください。
■必須管理点(CCP)判断の決定軸(※「CCPを確認するための決定樹の例」より抜粋+一部加筆)
質問1:この工程または以降の工程に、確認された危害要因を除去または低減するための管理手段は存在するか?
質問2:この工程は発生するおそれのある危害要因を許容レベルまで除去または低下させるために特に計画されたものか?
質問3:確認された危害要因の汚染が許容レベルを越えるか、または許容できないレベルまで増加する可能性があるか?
質問4:以降の工程は、確認された危害要因を除去するか、または発生し易さを許容レベルまで低下させるか?
よく必須管理点(CCP)に設定される工程としては、加熱殺菌工程や金属探知機の工程などがあります。もちろん、必須管理点(CCP)とみなされなかった工程についても、標準作業手順(SOP)や衛生標準作業手順に基づきしっかりと管理を行う必要があります。
※標準作業手順(SOP)とは、一般的衛生管理プログラムを実行するための具体的な標準作業のことで、衛生標準作業手順(SSOP)とは、SOPのうち、特に使用機器や手指の洗浄・殺菌、機器の衛生管理など、食品の取扱環境から危害要因の汚染や混入を防ぐための手順書のことです。
食品安全保証の最後の砦である必須管理点(CCP)
食品の安全性を保証するにあたって「最後の砦」だとされている工程が必須管理点(CCP)です。必須管理点(CCP)においては厳しい管理基準を設ける必要があります。また、必須管理点(CCP)はモニタリングをしっかりと行う必要があり、特に重要なポイントだけを見極めて、必須管理点(CCP)と定めることが大切です。
7原則12手順の一覧
- HACCPチームの編成
- 製品説明書の作成
- 用途、対象者の確認(加熱の有無など)
- 製造工程一覧図の作成
- 製造工程図をもとにした現場確認
- 【原則1】危害要因の分析
- 【原則2】必須管理点の設定
- 【原則3】管理基準の設定
- 【原則4】モニタリング方法の設定
- 【原則5】管理基準逸脱時の是正措置の設定
- 【原則6】検証方法の設定
- 【原則7】記録・保管システムの確立
※手順1~5は、原則1~7を進めるための準備となります。




